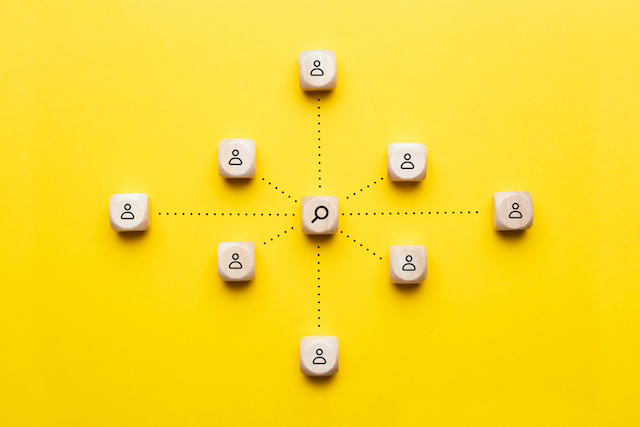弁護士向け|失敗しない外注ライターの選び方【9つのポイント】
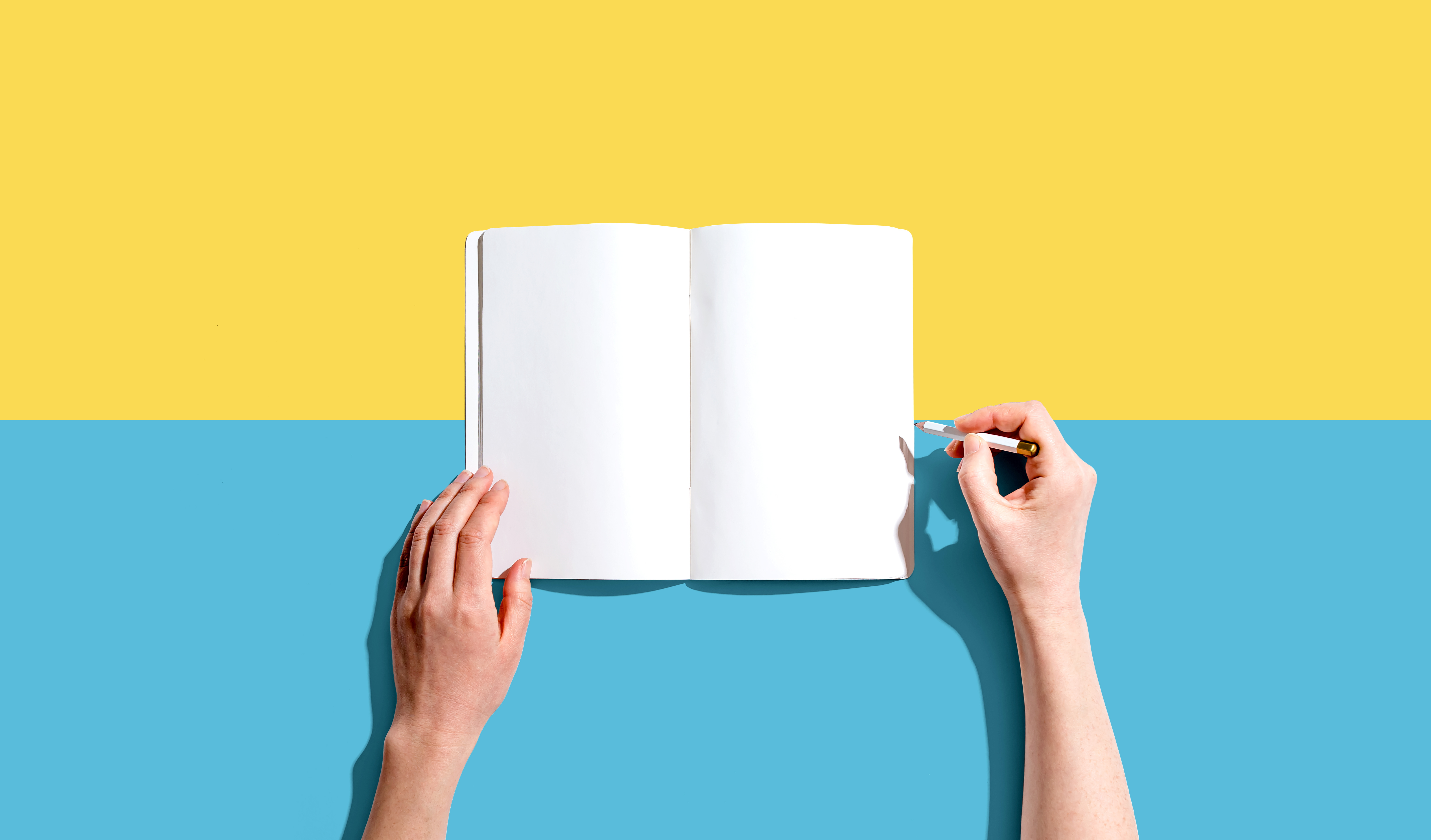
- 法律事務所のHP
- 交通事故、債務整理、離婚、相続などの特化サイトやブログ
こういった場所に載せる文章を、「ライター」に外注する弁護士は多いです。
しかし、法律に疎い方に頼んでしまうと、間違いだらけの文章を出来上がり、せっかく費用を払ったのに修正に時間を取られかねません。
また、他のHPから文章を盗用したり、著作権法を無視した引用などをすれば、事務所の信用を損ないかねません。
そこでこの記事では、「どんなライターに依頼すべきか?」というポイントをご紹介します。
主に弁護士向けですが、これから法律ライターとして活動したい方にもオススメの内容です。
本記事は、法律系ライター歴3年の紀村真利と、パラレルワーク弁護士の新井玲央奈の共同執筆です。
紀村 真利

慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、2016年からフリーランスのWebライターとして本格的に活動。2019年、法律系資格取得を決意したことをきっかけに、法律系ライターに転身。
法律記事のライティング、法律事務所HP内コンテンツの作成、弁護士ポータルサイトのコラム執筆、インタビューなど豊富な経験を有しています。
新井 玲央奈

弁護士として13年、これまで2,000記事以上のブログを書き、現在も月10万PV以上の個人ブログを運営。
法律事務所のHPや分野特化サイトの制作(サイト自体の制作及びライティング)、分野特化ブログのSEO対策及び記事制作などを経験してきました。
どんなライターに依頼すべきか?
まず言えることは、
- 法律系の資格を持っていないライターはダメ
- クラウドソーシングで発注すれば良い人が見つかる
そういう単純な問題ではないということです。
なぜなら法律ライティングには、専門知識とライティングスキルのバランスが求められるからです。
正確な知識があっても伝える力が足りないと、読者に伝わる文章は書けません。
ライティングスキルが高くても知識が乏しいと、不正確な記事ができてしまいます。
そこで、あくまでも我々の考えですが、法律ライティングを任せるのであれば、次のポイントを満たすライターが理想です。
もちろんこれは「理想」であり、全てを100%満たす方は稀だと思います(我々も完璧に満たしているとは思いません)。
「これらの条件を、できるだけ満たすライターに依頼する」という観点でご覧ください。
①任せたい分野について正確な知識を持っている、または、調べてしっかり書けること

法律ライティングでは、「間違ったことを書かない」というのが非常に重要です。
そこで、債務整理ブログなら債務整理の、交通事故サイトなら交通事故の、正確な知識を持っていることが理想です。
また、そこまでの知識がなくても、調べて正確なことを書けるスキルがあれば十分です。
「調べて正確なことを書ける」と言っても、これは簡単なスキルではありません。
基本書や実務書、判例を読む。あるいは条文を引く。こういった弁護士にとって当たり前のリサーチ作業が、大半のライターにとっては「ハードルが高いもの」だからです。
この時点で、法律ライティングを依頼できるライターはかなり限定されます。特に、刑事関係を書けるライターは意外にいないものです。
②ネット上にある法律知識の正誤を判断できること(少なくとも違和感に気付いて確認できること)
ネット上には、ライターが書いた文章が大量に存在します。
正直なところ、明らかな誤りがあったり、説明が不十分なサイトも結構あります。
ですから、その正誤を判断できるか、少なくとも「なんとなくおかしい」という違和感に気付いて、基本書や条文を確認できることが重要です。
③法律書・条文を確認する習慣があること
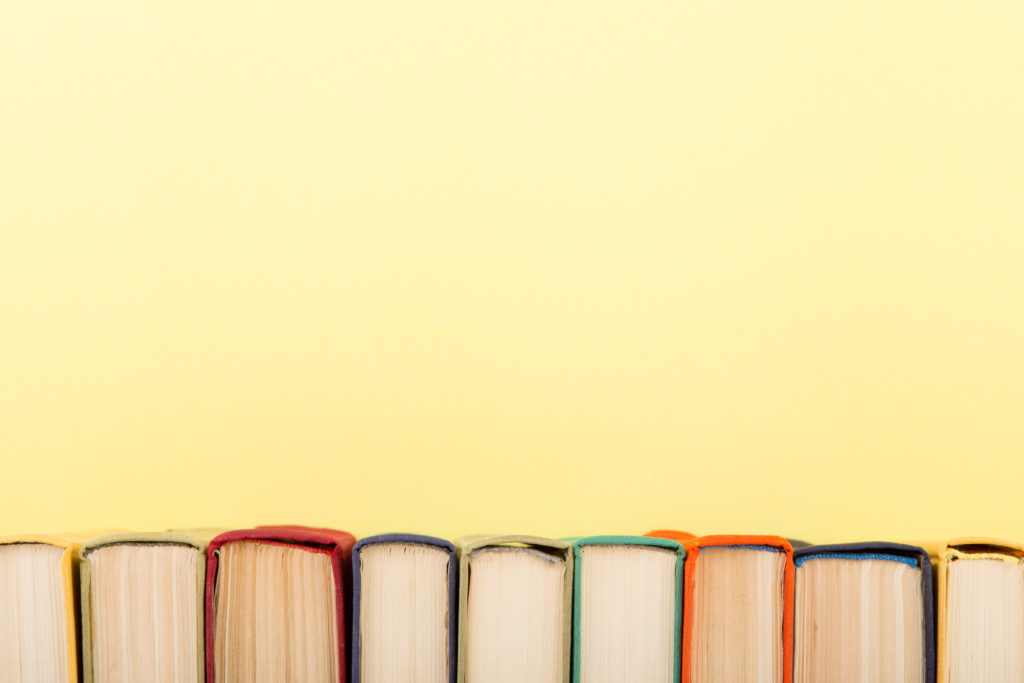
ネット上の知識を鵜呑みにしてしまうと、正確な法律知識を書くのは難しいです。
そこで、実務家や学者が書いた書籍、そして条文を確認する習慣が重要です。
弁護士なら基本中の基本ですが、この習慣が乏しいライターも少なくないはずです。
これらは、法的な素養に乏しいライターにとってハードルが高いこと。加えて、法律書は高額という事情も関係しています。
④法律書と条文を正確に理解できること
いくら確認しても、正確に理解できなければ意味がありません。
そこで、③を前提に、法律書や条文の内容を正確に理解するスキルが求められます。
①とも重なってくる話ですが、この時点で法律ライティングを頼めるライターはぐっと絞り込まれます。
⑤正確でありながら、一般の方にも伝わる文章を書けること
HPやブログの文章は、法律文書とは異なります。
法律用語をそのまま書いても理解されませんので、正確さを失わない限度で、短くしたり、適切な言い換えをしたりして、一般の方にも伝わる文章を書くスキルが求められます。
「わかりやすさ」と「正確さ」は一種のトレードオフの関係にあるため、一方の要素にこだわりすぎると「不正確」あるいは「正確だが読みにくい」ということになりがちです。
2つの相対立する要求をうまく両立させるためには、正確な法律の知識に加えて、日本語力やバランス感覚が必要になります。
ここは、もしかしたら一般のライターさんが優れているところも多い部分かもしれません。
⑥著作権や業務広告規程を理解していること

他のサイトから丸写しするのは論外ですし、文章や写真を引用する場合は著作権法上のルールを守る必要があります。
また、弁護士のHPやブログであれば、業務広告規程などを守る必要があります。
例えば、「絶対勝てます!」といった過度な期待を抱かせる表現や、過度な不安をあおるセールスライティングは控えなければなりません。
⑦ライター・社会人としての基本的なスキルやマナーがあること
法律ライティングに限りませんが、
- 納期を守ること
- 正しい日本語を書けること
- 連絡がちゃんと取れること
- クオリティにムラがないこと
- 誤字脱字が(ほとんど)無いこと
- SEO・WEBライティングの基本を理解していること
こういったことも重要です。
⑧実務的なことも書けること

法律事務所のHPやブログでは、実務的なことが書いてあると一気に厚みが増します。
もちろん、ここだけはクライアント(弁護士)が書くというのも一つですが、欲を言えば、ライターが書ければ大きいです。
弁護士ライターであれば実務的なことを書けますが、そうでなくても、パラリーガル経験のあるライターだと、ある程度書くことができます。
あるいは、実務経験のないライターでも、クライアントへのヒアリングや実務書で知識を補って書くことは可能です。
⑨インタビューやセールスライティングのスキルがあること
「あったらいいね」というオマケ要素の話になりますが、インタビューやヒアリング、コピーライティング/セールスライティングのスキルがあるライターは頼りになります。
特に、分野特化サイトのトップページなどを書くときは、コピーライティング/セールスライティング系の知識が求められるでしょう。
また、パンフレットにインタビュー記事を載せたいときはインタビュー経験があるライター、プレスリリースを打ちたいときは広報系の経験があるライター、PR動画を作りたいときは動画制作経験のあるライターが強みを発揮します。
ひとくちにライターと言っても、さまざまなキャリア・経験を積んできた人材がいます。
ライター側の経験値が高ければ高いほど、さまざまな種類の仕事を一括で依頼することが可能になります。
ご依頼・ご相談お待ちしております
紀村・新井ともに、法律ライティングの依頼を受け付けております。ご相談や見積り依頼も大歓迎です。
それぞれのTwitter、note、HPからご連絡ください。
紀村
新井
まとめ
弁護士が、HPやブログのライティングをライターに外注する時、「どんなライターに依頼すべきか?」というポイントをまとめました。
次回は、「実際に、どういう風に良いライターを探すべきか」について解説します。